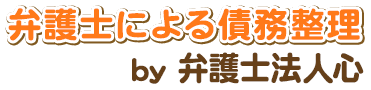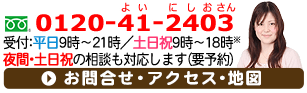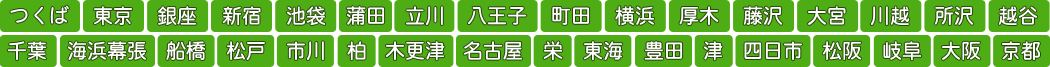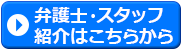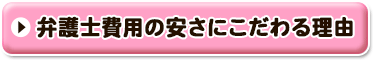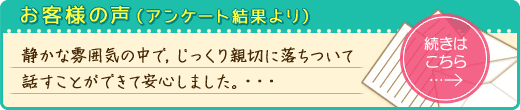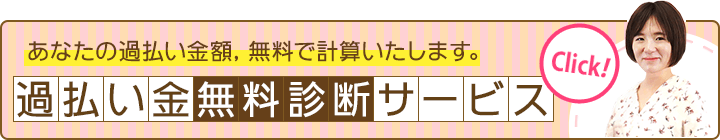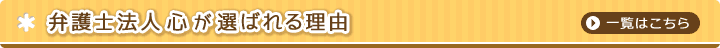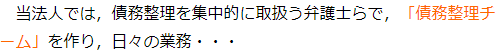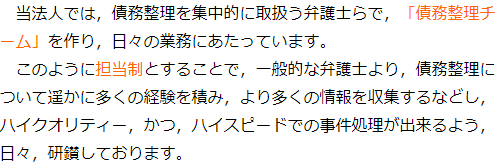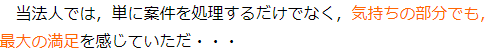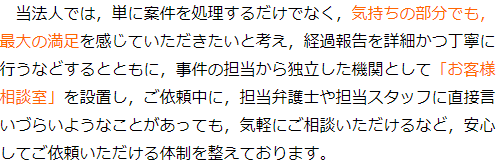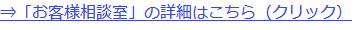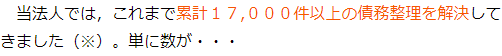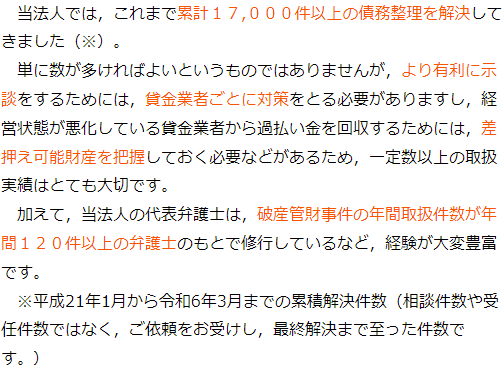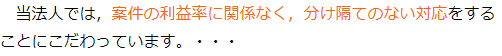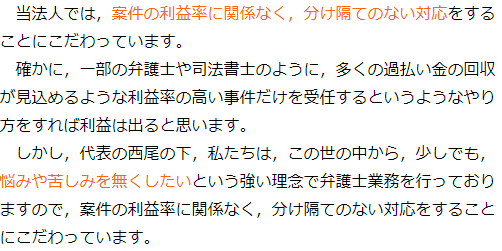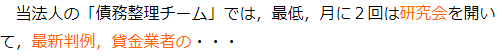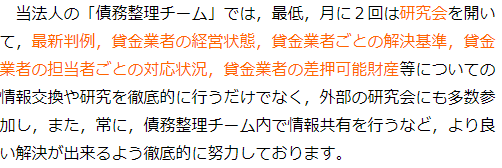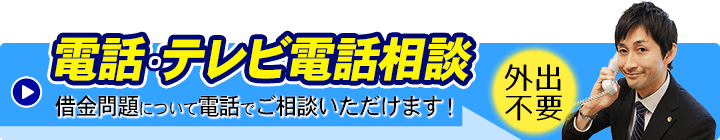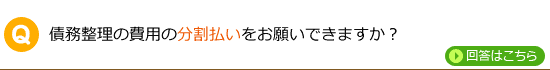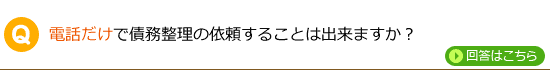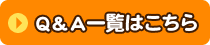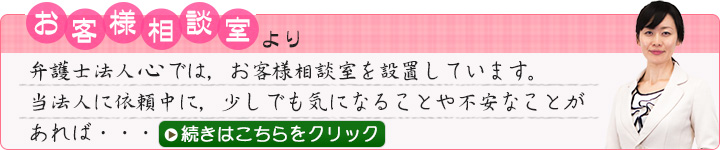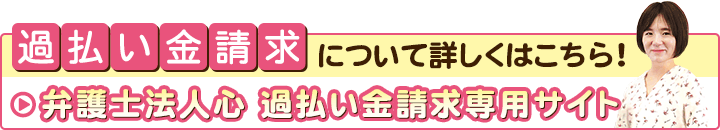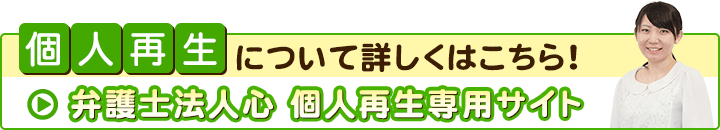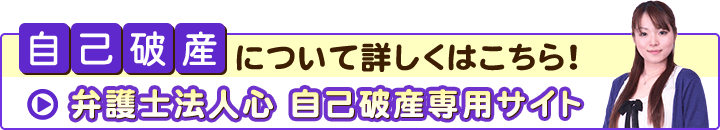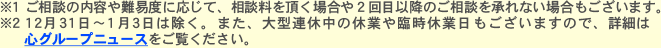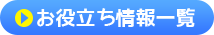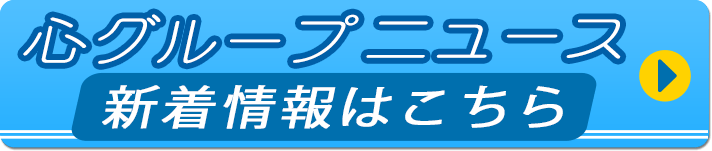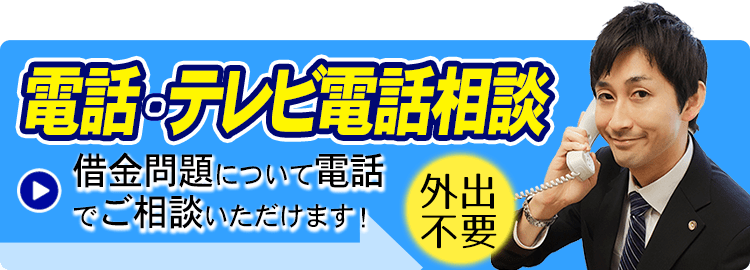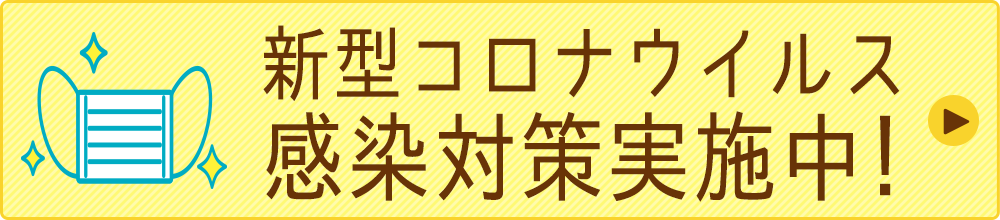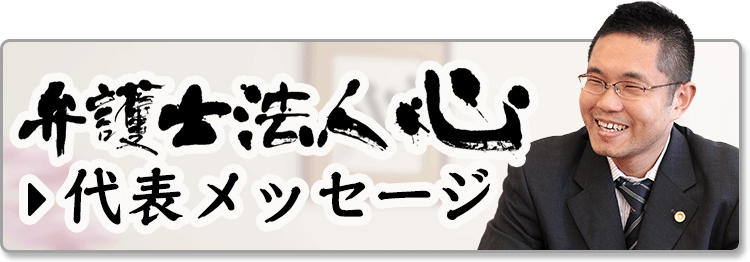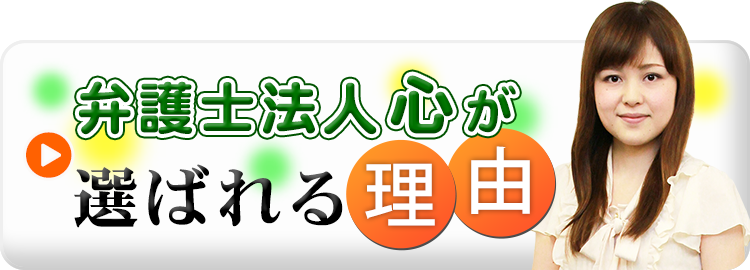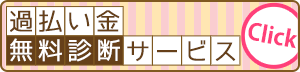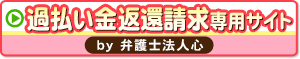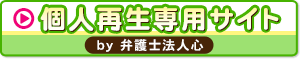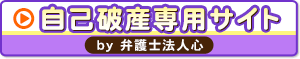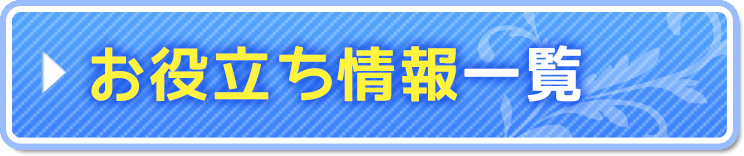-
債務整理における直接面談義務とは,債務整理(すなわち,自己破産,個人再生,任意整理,完済した方以外の過払い金返還請求)については,原則として,弁護士が,依頼者様に対して,直接,面談して,重要事項の説明等をしなければならないという義務の・・・ 続きはこちら
-
セカンドオピニオンとは,すでに弁護士に依頼している事案についての別の弁護士の意見のことをいいます。簡易な案件で特に争点もないような事案であれば,どの弁護士に頼んでも,結論は変わらないと思われますが,専門的知識が必要な事案や争点がある事案・・・ 続きはこちら
-
非弁提携弁護士・司法書士とは,弁護士法等に違反している者と提携している弁護士・司法書士のことをいいます。提携とは,簡単にいいますと,主に,弁護士が,①有料紹介を受ける場合と,②弁護士名を使わせる場合があります。いずれの場合も,当然・・・ 続きはこちら
-
グレーゾーン金利とは,①利息制限法で認められている上限利率と②出資法で認められている上限利率との間のことをいいます。①利息制限法の上限利率は,借入金が,100万円以上の場合は15%以下,100万円未満10万円以上の場合は18%以下,10万・・・ 続きはこちら
債務整理についてご紹介
お役立ち情報として様々な情報を掲載しています。具体的な内容や、自分の状況に当てはめた情報を詳しく知りたいという方は、弁護士にご相談いただければと思います。
サイト内更新情報(Pick up)
2024年4月8日
債務整理
債務整理を行うのに適切な時期
債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産という3種類があります。債務整理を開始するタイミングによって、取ることができる方針が変わってくる場合があります。・・・
続きはこちら
2024年3月5日
自己破産
破産管財人の役割・権限・支払う報酬について
自己破産の手続には、破産開始と同時に破産管財人が選任される管財事件と、破産開始と同時に手続が廃止される同時廃止事件があります。一般消費者の方が破産される場合、破産管財人・・・
続きはこちら
2024年2月2日
個人再生
住宅ローン特則について
個人再生手続を行い再生計画が認可決定されると、その後は再生計画で定めた内容に従って返済を行っていくこととなります。しかし、個人再生をした場合でも、抵当権などの担保権は、・・・
続きはこちら
2024年1月17日
過払い金の計算の仕方
平成22年の貸金業法等の改正まで、貸金業者の中には、利息制限法で定められた法定の利率以上の利息をとっていたところがありました。 つまり、法で定められていた利息よりも多くの・・・
続きはこちら
2023年12月5日
任意整理
任意整理にかかる期間と流れ
任意整理には、通常、短い場合は3か月、長い場合は9か月くらいの期間がかかります。。ただし、事案によってはもっと長い期間がかかることもあります。任意整理では、まず話し合い・・・
続きはこちら
更新情報のご案内
債務整理に関するお役立ち情報は、随時更新しております。こちらで更新情報をご案内しておりますので、手続き等について関心がおありの方はご覧ください。
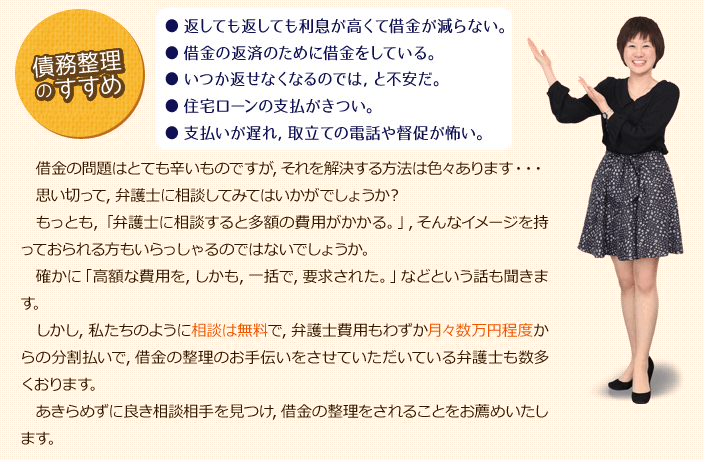 続きはこちら
続きはこちら
借金でお悩みの方へ
借金の返済にお悩みの方は、当法人に一度弁護士にご相談いただき、債務整理をご検討ください。当法人の弁護士がしっかりと対応させていただきます。
債務整理にもいくつかの手続きがあります
それぞれの債務の状況によりどの手続きによるべきかが異なりますので、まずは当法人の弁護士にご相談ください。適切と考えられる債務整理の方法をご相談の際に弁護士からお話しさせていただきます。
お近くの事務所でご相談いただけます
名古屋市内に複数の事務所がありますので、ご予約の際にお近くの事務所をご指定ください。いずれの事務所も利便性の良い場所にあります。
債務整理を弁護士に依頼するタイミング
1 債務整理を行うタイミング
債務整理を行うにあたり、必ずこのタイミングでなければならないというものはありません。
以下では、個人の方が債務整理を弁護士に依頼するタイミングとして、具体例をいくつか挙げていきます。
2 債務整理の具体例
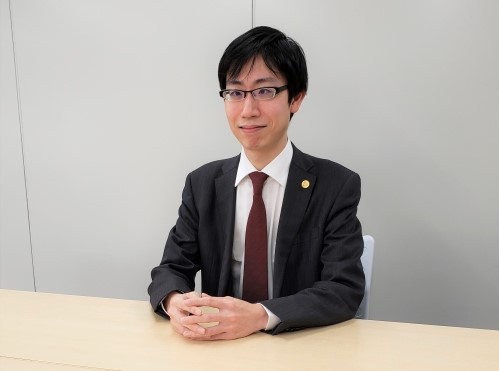
⑴ 借入れが年収の3分の1を超えてしまった場合
一般に、借入れが年収の3分の1を超えてしまった場合、借金を返済することは困難です。
このような場合には、家計的にもかなり苦しく、毎月の返済にも支障をきたしていると考えられます。
そうなってくると、借金を返すためにさらに友人、知人、親族から借入れを行ってしまうという例が多くあります。
このような事態になる前に、早めに弁護士に債務整理を依頼することが得策です。
債務整理の中でも、自己破産という基本的に返済義務が免除されるような手続や、個人再生という借金を減額する手続を行う場合、もしも知人や友人等に対して優先的に返済してしまっていると、この点を裁判所が問題にして、手続上不利に扱われることもありますので注意が必要です。
そうなると債務整理の手続が複雑になってしまい、より多くの費用や時間がかかってしまうことがあり得るため、そうなる前にご相談いただく必要性が高いといえます。
⑵ 収入が減る場合やなくなってしまう場合
この場合、借入れのときに前提としていた返済計画が成り立たなくなってしまっています。
借金を返すあてがなくなってしまい、これを放置すると、お金を借りている相手から連日のように督促が来たり、裁判所から訴状が届いたりする可能性があるため、早期に弁護士に債務整理を依頼することを推奨します。
3 お早めに弁護士に相談を
どのような債務整理をどのタイミングですることが適切かという点については、債務者の方それぞれの事情があり、お話をうかがってから弁護士が判断することになります。
まだ大丈夫だろうと思っていたが、実はすぐに債務整理を始めることが適切であったというケースは、意外に多くあります。
債務整理をすべきかどうかお悩みの方は、当法人にご相談ください。
債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 弁護士に依頼すると債権者からの督促を受けなくて済む

債務整理は、法律上は、弁護士等の専門家に依頼することなく、ご自身ですることも可能です。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく3種類あります。
どの手続きでも共通するご自身でするメリットは、弁護士費用がかからないことです。
弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士が各業者に通知を出すと、ご自身で督促を受けなくて済むということです。
貸金業法で、弁護士等の専門家が代理人になる旨の通知を受け取った貸金業者は、弁護士等に連絡をとらなくてはならず、ご本人に督促してはいけないことになっているからです。
2 任意整理では、差押えの受けやすさや利率・返済額に違いが出る
任意整理は、相手の業者と分割払いの話し合いをすることです。
ご自身でする方も一定数いらっしゃいますが、相手の業者はその道のプロですから、ご自身でやると、毎月の返済額を十分払えるまで減らす合意が出来なかったり、返済額が少ないと今度は利息ばかり払う状態にされ、ほぼ元金が減らないという状態になりがちです。
業者によっては、弁護士を介入させない場合は、事実上分割払いの交渉に応じないところもあります。
弁護士に依頼することで、利息を減額してもらえたり、返済額を抑えやすくなります。
3 自己破産をご自身でやるには、破産に至る経緯やお金の流れを書面で十分に行える必要がある
自己破産は、裁判所に申請して借金を0にしてもらう手続きです。
費用がもったいないと考えてご自身でやる方もまれにいらっしゃいます。
しかし、破産には同時廃止と管財事件と2種類ありますが、ご自身でやると、破産に至る経緯やお金の流れの説明が不十分になり、また、破産法上求められる資料の準備ができず管財事件になりがちです。
管財事件になると、裁判所に支払うお金が20~40万円程度かかります。
管財事件の場合、裁判所から選任された破産管財人と呼ばれる弁護士が付きます。
管財人の事務所へ行き面談を行ったり、裁判所での債権者集会を行う必要があります。
弁護士に依頼をすることで、同時廃止で破産を申立てることが可能となります。
なお、同時廃止の場合は、管財人との面談や裁判所での債権者集会もありません。
また、一見普通におこなっているお金の動きも不適切と判断され、その分を弁償しなければ借金が0にならない等の問題が生じ、破産を諦めている方もいらっしゃいます。
4 個人再生をご自身でできる人はほとんどいない
個人再生は、裁判所に申請して借金を減額してもらい、3~5年の分割で払う手続きです。
提出をする書類の種類も多く、申立書に自身で記入する欄も複雑であり、経験の無い人が手続きの準備を行うことは、難易度がかなり高いとされています。
個人再生をご自身でやった方をほぼみたことがありません。
これは、減額できる金額が、借金額以外に財産の評価額も考慮されて計算が複雑であることや、裁判所に何度も違う書類を出さなければならない点にあるようです。
個人再生の手続きが開始され、再生計画案を作成します。
再生計画も作成に慣れている人でなければ、難しいものになります。
債務整理で利息が0になった場合にどのくらい支払いが減るか
1 債務整理で将来の利息が基本的に0になる

債務整理で最も多く行われているのは、弁護士が相手の業者と話し合いをして、長期分割を認めてもらうという方法です。
この方法は、専門的にいえば任意整理といい、おおむね5年分割で元金のみ返すのが目安になります。
ここでは、事例をもとに、利息が0になることでどれくらい支払いが減るのかを、簡単な計算でみていきます。
2 事例
例えば、貸金業者Aから、200万円を利率12%で借り入れて、毎月4万円返済しているとします。
任意整理をすることで、元金200万円はそのままですが、利率を0にしてもらい、毎月の返済額が5年分割60回払いで月額3万4000円(200万÷60回)になったとします。
この場合、毎月の返済額が6000円減るだけでは物足りなく思う方もいらっしゃるかもしれませんが、利息が12%から0になった効果は、大きいものがあります。
3 約束どおりの返済では、毎月2万円しか元金を返済していない
一般に、利率12%というときは、1年間に相手の業者がとる利息のことを指します。
Aは、200万×0.12=24万円の利息を1年間でとります。
毎月に直すと、24万÷12ヶ月=2万円です。
そうすると、毎月4万円返済しているようにみえても、元金は2万円しか払っておらず、利息で毎月2万円とられていることになります。
4 利息が0になると、1年だけでも24万円も支払いが減る
利息が0になると、毎月2万円の利息がなくなりますので、1年間では24万円も払う金額が減ることになります。
これが5年間続けば、120万円支払いが減ることになりますし、実際約束どおり返済する場合は、もっと返済期間が長くなります。
5 返済が進まずお困りの方はご相談ください
この計算は、利息をあまり考えてこなかった方にもイメージしていただきやすいように簡単にしたもので、元金の減少を考慮していないため、正確とはいえません。
それでも、利息をまけてもらうことで、いかに支払い額が減るのかをイメージしていただけると思います。
利息ばかり払っていていつまでたっても借金が減らないとお考えの方は、気軽に弁護士までお問い合わせください。
任意整理が成功しない場合と解決策
1 任意整理に失敗すると返済額が減らない

任意整理は、返済が難しくなってしまった場合に、依頼を受けた弁護士が債権者と交渉して、長期間での分割払いを提案したり、利息をカットしてもらったりして、毎月の返済額を減らし、返済までの道筋をつけていくというものです。
これは、法律に規定された手続きではなく、債権者との合意によって成立するものなので、債権者が利息のカットや分割の組みなおしに応じない場合には、従前の内容と変わりがない、もしくは分割の組みなおしができず、一括での返済を求められることもあります。
このような場合は任意整理をしても返済額が減らない、もしくは増えてしまうということになるので、任意整理の失敗といえます。
2 任意整理が失敗する場合
会社として任意整理を受け付けない方針をとっている業者の場合、任意整理の交渉を持ちかけても、断られてしまいます。
任意整理はあくまでも当事者間の合意によって成立するものである以上、債権者が交渉に乗らない場合には、任意整理ができません。
また、借入れから任意整理するまでの期間が短い場合には、交渉を拒否され、任意整理が失敗することもあります。
3 対処法
このような場合の対処方法としては、自己破産や個人再生の手続を申し立てることが考えられます。
自己破産や個人再生であれば、法律の規定に従って債務が減額もしくは免除されることになるので、一部の債権者がどれほど利息のカット、債務の減額もしくは免除に反対したとしても手続きを進めていくことができます。
ただし、小規模個人再生の場合には、債権者の頭数の半数かつ債権額の半額の債権者反対がないことが要件となっているので、このような債権者の反対が見込まれる場合には、小規模個人再生以外の手続を選択する必要があります。
また、借入れから自己破産・個人再生をするまでの期間が短いと、返済能力がないのに借入れを行ったとして、不利な事情としてとらえられてしまうおそれもありますので、注意が必要です。
4 まとめ
任意整理の交渉をしてみたが、支払能力を超える金額でしか合意が得られない場合や、債権者が任意整理に応じないような場合には、個人再生や自己破産の手続きに切り替えることになります。
そのため、任意整理が無理だった場合には個人再生や自己破産等に切り替えることもありうるので、そのようなことが可能かどうか依頼前に確認しておくのがよいでしょう。
弁護士法人心では、任整整理、個人再生、破産手続き全てについて経験豊富な弁護士が在籍しています。
名古屋で債務整理をお考えの方はぜひ、お気軽にご相談ください。
借金問題を弁護士に相談した場合の流れ
1 相談

借金でお悩みの場合、弁護士に相談したらどのような流れになるのでしょうか。
まず、借金の問題を相談された弁護士は、現状を把握し、どのような手段をとることができ、どんな解決を図るべきかを相談者と考えていくことになります。
2 受任通知
相談の結果、依頼いただくことになった場合、弁護士は依頼を受けた件について、対象となる債権者に受任通知を送ることになります。
受任通知の効果は、単に弁護士がついたということを債権者に報告するというものだけではありません。
貸金業者やクレジットカード会社が弁護士から受任通知を受け取った場合は、原則として、本人と直接連絡を取ることができなくなり、弁護士を介して連絡を取ることが必要になります。
そのため、支払が遅れていたとしても、債権者からの督促の連絡が来ることがなくなります。
3 支払いの停止
また、任意整理であれば、ご依頼いただいた債権者については、法定の利率以上の取引がある場合にはこれを法定の利率に引き直した上で、分割支払の交渉をしていくことになります。
この交渉の際に、対象となる債権の額等が変動するのは好ましくないので、支払をいったん止めた上で交渉していくことになります。
破産や個人再生の場合は、ある特定の債権者に対してのみ返済をすることは偏頗弁済として禁止されているため、全ての債権者への返済を止めることになります。
そのため、債権者からの督促や支払いに追われることのない状態で生活を立て直すことができます。
最終的には、任意整理では、債権者と分割支払いの和解をして支払いを継続していき、破産者や個人再生であれば、裁判所への申立ての準備を進めていくことになります。
4 まずはお気軽にご相談ください
以上が、弁護士に借金問題等について相談した場合の大まかな流れになります。
ただ、どのように手続きを進めていくかは一人ひとりの状況によって異なります。
まずは、お気軽にご相談ください。
当法人は、名古屋駅のすぐ近くに事務所がありアクセスは抜群です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
債務整理の相談で通帳がある方がよい理由
1 家計の収支が把握しやすい

債務整理の件でご相談いただき、ご事情等を把握させていただいた後には、相談者の方の状況にあった方針を決定していくことになります。
通常、弁護士に債務整理をご依頼いただく場合、方針としては、自己破産・個人再生・任意整理のいずれかになることがほとんどです。
そして、任意整理や個人再生の場合には、債務が全てなくなることはなく、支払いを継続していく必要があります。
そのため、任意整理や個人再生の方針で進めていくためには、毎月いくら払っていくことができるかを確認する必要があり、収入と支出を確認させていただき、毎月いくらを債務の返済に充てることができるかを把握する必要があります。
通帳があれば、通常、そこから収入の金額や、光熱費等の口座振替になっている支出を把握することができるので、毎月の収入と支出を把握することの助けになることが多いです。
たとえばある口座に、給料が毎月20万円振り込まれ、水道光熱費が1万円、家賃が6万円、保険料が2万円引き落とされているとします。
あと食費が5万円、ガソリン代が2万円と見積もれば、毎月返済できる額は、4万円(20万-1万-6万-2万-5万-2万)と考えることができます。
2 相談者が意識していない債権者の把握
通常、相談の際は、すべての借入先等をうかがいます。。
これは、任意整理で、債務整理を希望する債権者のみを受けたとしても、それ以外の債権者に影響がでることもあることと、個人再生・自己破産の場合には全ての債権者を対象にしなければならないからです。からです。
ただ、家賃のみを支払っているクレジットカード等については、相談者の方が債権者として認識しておられないこともあります。
このように債務者の方が認識しておられない債権者についても、口座振替であれば通帳の記載から確認することができ、問題が生じることを避けることができます。
たとえば、オリエントコーポレーションのカードで家賃の引き落としをしている場合、オリエントコーポレーションの引き落としが毎月通帳に現れることで、対応を検討しなければならないと分かります。
3 自己破産・個人再生で問題ある入手金の対応を検討する
自己破産や個人再生の場合には、財産や収支の状況等を裁判所に報告する必要がありますので、通常、通帳のコピーを提出する必要があります。
当然、通帳の記載内容によっては、裁判所に内容を問題視されることがあり、なんらかの手当をする必要が生じることもあります。
そのため、相談時に通帳等をお持ちいただき、内容を確認することにより問題点の有無や、問題点がある場合にはその対処法を早期に確認することができ、手続きの選択やその後の手続きがスムーズに進むことになる可能性が高いです。
4 債務整理をお考えの方はご相談ください
それ以外にも、通帳を確認させていただくことのメリットはございます。
したがって、債務整理でご相談の際は、通帳をお持ちいただけると助かります。
通帳がないネット銀行の場合は、入出金履歴を出力するか、打ち合わせで見ることができるようログインパスワード等を確認しておくのがよいでしょう。。
弁護士法人心では、債務整理の相談料は基本的に無料となっております。
名古屋近郊で債務整理をお考えの方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
債務整理の相談で収入と支出を把握する必要がある理由
1 債務整理における収入と支出の把握の必要性

弁護士に債務整理を依頼する場合、その方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
任意整理では、利息を払い過ぎており過払い金が発生しているような場合を除いて、元金等を分割払いしていく必要があるので、その支払いができるだけの支払能力が必要になります。
個人再生は、一定の金額に借金等が減額された上で、その金額を分割払いしいくという手続きですから、任意整理よりは払わなければならない金額は減るのが通常ですが、減額後の借金を分割払いできるだけの支払い能力は必要となります。
自己破産では、借金の支払義務がなくなるので、全く支払能力がなかったとしても、手続きを進めていくことができます。
このように、支払能力の大きさによって、どのような手続きを選択することができるかが決まってきます。
そのため、債務整理の相談をいただいた際に、収入と支出を把握する必要があります。
2 手続ごとの事情
また、支払能力の把握以外に、手続毎に細かく把握しておいた方がいい事情もあります。
⑴ 任意整理の場合
任意整理の場合、一定以上の支払能力があるのであれば、収入と支出の細かい内訳まで把握しておく必要性は低いといえます。
しかし、債権者も貸したお金は早く返してほしいと考えるのが通常ですから、収入が大きい場合には短期間での返済を求められる場合もあります。
その場合、収支の内訳を債権者に伝え、支払可能額がこれだけしかないということを主張し、交渉していくことにより、長期間で月々の返済金額を抑えた分割方法での和解をまとめていけることもあります。
そのため、毎月の支払いに充てられる金額が、任意整理が成功するかどうか微妙なラインの場合には、細かく収入と支出を把握させていただくこともあります。
⑵ 自己破産、個人再生の場合
自己破産、個人再生の場合には、月々の収入と支出を裁判所に報告する必要があります。
個人再生の場合には、減額された後の借金等の支払能力があるかどうかを把握する意味合いで収支状況の把握はとても重要です。
自己破産の場合には、自己破産が成功した場合には借金の支払義務はなくなりますので、支払能力の有無はさほど重要ではありませんが、裁判所が自己破産を認めるかどうかを判断する一つの要素にはなり得ます。
例えば、自己破産に至った原因が浪費やギャンブル等にある場合には、そのような無駄遣いをせずに生活できているかを見ることによって、しっかりと反省できているかという観点から、自己破産を認めるか否かの判断がなされるのです。そこで相談の段階から、収入、支出を細かく教えていただくことにより、個人再生における支払能力があるかどうか、自己破産において浪費とみなされるような無駄遣いはないかどうかなどをあらかじめチェックし、収支のバランス改善のためのアドバイスをすることで自己破産や個人再生の手続きを成功させるための準備を進めていくことができます。
3 債務整理のことは当法人にご相談ください
このように、任意整理と自己破産・個人再生では理由は違いますが、いずれも相談の段階で、収入と支出を把握している場合にはご相談がスムーズに進みます。
弁護士法人心は、名古屋駅のすぐ近くに事務所を構えております。
お気軽にご相談ください。
転職が債務整理に与える影響がご心配な方へ
1 はじめに
債務整理を依頼後に転職する場合、債務整理の手続きにはどのような影響があるでしょうか。
転職の影響は手続によって異なります。
2 任意整理の場合

任意整理とは、依頼を受けた弁護士が各債権者との間に入り、今後の支払方法について交渉していくものになります。
任意整理を行う場合、各債権者への返済原資を確保することができるのであれば、交渉中に転職等があったとしても問題にならないことがほとんどです。
反対に、各債権者への返済原資を確保することが難しくなりそうであれば、破産や個人再等の手続きへの変更も検討する必要があります。
3 個人再生の場合
いわゆる個人再生の手続きには、小規模個人再生の手続きと給与所得者等再生の2種類があります。
このうち、給与所得者等個人再生は、定期的に収入を得ることができ、かつ、その変動の幅が少ないことが要件となっています。
変動の幅が少ないかどうかの確認は、過去2年分の給与等を比較し、5分の1以上の変動があるかどうかによって行うことが多いです。
そのため、転職等があると、収入の変動の幅が少ないかどうかの判断が難しくなり、給与所得者等個人再生の要件を充たさないと判断される可能性があります。
小規模個人再生の場合にも、法律によって減額された債務の返済が履行できる見込みがあることが必要になるので、転職によって収入が変動する場合には、再生計画の履行可能性がないと判断される可能性もあります。
4 自己破産の場合
破産の場合については、生命保険の募集人等、自己破産の手続き中に就業の制限がかかる仕事に転職するのでなければ、転職による影響は生じないことが多いです。
5 詳しくはご相談ください
ここでの転職の影響は、あくまで一般的なものになります。
個人個人の事情によっては、転職によってここで上げた以外の悪影響が出ることもあります。
そのため、詳しくは、弁護士にご相談ください。
当法人には、債務整理を得意とする弁護士がいます。
債務整理をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
支払いが可能でも弁護士に債務整理を依頼した方がよい場合
1 なんとか支払いができているという方へ
余裕があるわけではないものの、どうにか返済をしていくことはできる。
そのような状態であっても、債務整理をした方がよい場合もあります。
まずは、債務整理のデメリット・メリットを考えてみましょう。
2 債務整理をするデメリット

債務整理のデメリットとして、信用情報機関に事故情報が載ってしまうということがあります。
事故情報が載ると、新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなってしまいます。
また、破産や再生の場合は、全ての借入れやクレジットカードを対象にする必要があるのですが、任意整理であれば、対象とする借入れやクレジットカードを選ぶことができます。
しかし、信用情報機関に事故情報が載ってしまいますと、対象としなかったクレジットカード等についても新たに利用することができなくなってしまい、返済のみをしていくことになる可能性があります。
また、破産、再生の場合には、裁判所に申し立てをすることになり、これ以外にも様々なデメリットが存在します。
3 債務整理をするメリット
債務整理のメリットとして、債務を完済する見通しを明確にすることができるということがあります。
自己破産であれば、免責許可決定が確定すれば、借金等を返済する義務はなくなるので、当然、債務を完済したのと同じ状態になります。
個人再生であれば、通常であれば債務が減額され、3年から5年間の支払いで完済するという再生計画を立てることになります。
任意整理でも、通常であれば今後発生する利息をカットしたり、減額したりすることにより、これまでの返済よりも支払いを減額していくことができます。
したがって、債務整理を行えば完済までの道筋を作ることができます。
4 支払いが可能でも債務整理をした方がよい場合
⑴ 新たな借入やローンが不要な場合
以上のとおり、債務整理のデメリットは、信用情報機関に事故情報が載ってしまうことにより、新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなることです。
これに対して、債務整理のメリットは完済までの道筋を建てることができることです。
そのため、新たな借り入れやローンを利用していく必要がない場合には、債務整理のデメリットは大きく軽減されます。
そこで、なんとか支払いができる状態であっても、新たな借入やローンを組めなくてもよい場合であれば、債務整理をした方がよいといえると思います。
⑵ 借入やクレジットカード利用がなければ生活費が捻出できない場合
なんとか返済はできているものの、その返済により生活費にあてる現金がなくなり、生活のために借入やクレジットカードの利用をしなければならない人がいます。
これでは、返済をしていても借金が全く減らず、債務を完済するまでの道筋が立ちませんし、いつか貸してくれる業者がいなくなって返済できなくなります。
⑶ 利息ばかり払っている場合
一般の消費者金融やクレジットカードの利率は、年10%を超えるものも多いです。
たとえば、120万円借りて年10%の利息がつく契約なら、1年に12万円、1ヶ月に1万円(120万×0.1÷12)の利息を払うことになります。
毎月1万5000円返済していても、利息に1万円とられ、元本は5000円しか返していないので、完済まで何年かかるか分からないぐらいです。
⑷ 借入をして別の借金返済にあてている場合
給料からでは返済に回すお金が足りない場合、A社の借金を返済するため、B社から借金することになります。
一見借金の返済はできていますが、これでは借金は増える一方で減ることはありません。
いつかどの業者も貸してくれなくなり、借金返済ができなくなります。
そこで、借入をして別の借金返済にあてている場合は、債務整理をした方がよいといえます。
当法人は、名古屋駅のすぐ近くのアクセス抜群の場所に事務所があります。
借金の返済等でお悩みの方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
債務整理を依頼するなら、弁護士と司法書士の違いをチェック
1 専門家の違いを知っておきましょう

債務整理を専門家に依頼する場合、相談先の候補としては弁護士と司法書士がいます。
しかし、弁護士と司法書士では何が違うのかという点について、知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこで、債務整理における、弁護士と司法書士の違いをご説明します。
2 債務整理を扱えない司法書士もいます
司法書士の資格を持っていたとしても、必ず債務整理を扱えるというわけではありません。
司法書士は、本来、不動産の登記や会社関係のいわゆる商業登記の名義を変える手続きを専門に扱っており、債務整理の分野は扱えないのが原則です。
しかし、法務大臣から認定を受けた、認定司法書士であれば、一定の範囲で、債務整理を行うことができます。
3 弁護士と司法書士では、権限が異なります
弁護士は、ご依頼者様の代理人になることができるため、制限なくご依頼者様の権利の行使や義務の履行などができます。
つまり、債務整理に関する業務に制限がありません。
弁護士は、たとえ、借金が何億円あったとしても、ご依頼者様に代わって債務整理を行うことができます。
他方、司法書士には、140万円という壁があります。
司法書士は、個別の債権額が140万円以下の場合に限り、交渉などを行うことができると、法律で定められています。
そのため、司法書士は、個別の債権額が140万円以上の案件を扱うことができません。
自分はそれぞれ140万円以下の借入しかないから司法書士でも問題ないとお考えの方も、落とし穴があります。
たとえば、三井住友銀行から100万円、住信SBIネット銀行から50万円を借りている方が債務整理すると、どちらも保証会社であるSMBCコンシューマーファイナンスと交渉することになるケースが多いです。
この場合、SMBCコンシューマーファイナンスに150万円の債務があることになり、司法書士では交渉できなくなります。
このように、複数の業者から借りて総額140万円以上の債務がある方の中には、司法書士では交渉できなくなり、結局別に弁護士に費用を払って依頼することになるケースもありますので、注意が必要です。
また、今の借入は1社で50万円しかなくても、調べてみると過払い金が150万円あるケースもあります。
このときも、過払い金が1社で140万円を超えるので、司法書士では取り返すのが難しくなります。
4 裁判所とのやりとりの仕方に違いがあります
債務整理の中には、裁判所の関与のもとで、進められる手続きがあります。
弁護士であれば、裁判所とのやりとりについても、全て代理人として行うことができます。
そのため、仮に裁判官から呼び出され、事情を説明しなければならないような場合でも、弁護士が代理人として代わりに説明をすることができます。
他方、司法書士は、代理人になることができる場面が限られているため、ご依頼者様が自分で裁判官に説明をしなければならないケースがあります。
裁判所とのやりとりでは、破産法や民事再生法の解釈や運用を前提に、専門的な質問がなされることが多いことから、弁護士でなければ適切な回答ができないことも多くあります。
適切な回答ができない場合、裁判所が不利益な判断をする可能性があります。
裁判所から債務に関する書類が届いたら
1 裁判をされると裁判所から書類が送られてきます

借入等の返済ができず、債権者への連絡もできないままでいると、債権者から裁判を起こされることがあります。
裁判を起こされると、裁判所から郵送で書類が送られてきます。
これは特別送達という方法で郵送され、不在の場合は不在票がポスト等に入れられているので、保管期間内に受け取ることができないと裁判所に返送されることになります。
2 裁判所からの書類を受け取ることができないとどうなるか
裁判所からの書類を保管期間内に受け取ることができない場合、今度は、付郵便送達という方法で書類が送られる可能性があります。
この方法で書類が送られた場合、裁判所が発送した時点で、書類を受け取ったとみなすことになります。
そのため、今度は保管期間内に受け取ることができなかったとしても、法律上は受け取ったものとみなして手続きが進んでいってしまうことになります。
3 裁判所から届いた書類を無視した場合
裁判所から届いた書類を無視した場合、もしくは、付郵便送達で送られた書類を受け取らなかった場合、手続きは進んでいくことになります。
この場合、なんの反論もしなかったということになり、訴えた側の主張がすべて認められることになります。
そのため、裁判等を起こされていた場合、訴えた側の主張をすべて認める判決が下されることになります。
4 裁判所から書類が届いたら弁護士にご相談ください
このように、裁判所から書類が届いたのを無視していると、相手方の主張がすべて認められてしまうことになります。
そのため、裁判所から書類が届いたらすぐに弁護士に相談する必要があります。
仮に、実際に借入等をしていて、返済の義務があったとしても、弁護士を立てることにより、相手方と裁判上で交渉して分割での返済を可能としたり、破産や個人再生の申立てをしたりすることができます。
また、最後に支払いをしてから時間が経っていれば、時効により債務は消滅したとの主張が認められることもあります。
当法人は、名古屋駅のすぐ近くに事務所があり、ご予約の日時も平日夜間や土日祝日を含め柔軟に調整していますので、お忙しい方にもご相談いただきやすいかと思います。
裁判所から書類が届いた方は、お早めに当法人までご相談ください。
債務整理に強い弁護士にご相談ください
1 なぜ債務整理に強い弁護士に相談した方がよいのか

弁護士は、様々な分野を取り扱うことができる反面、全ての分野について高い専門性を持ち合わせることは困難です。
そこで、債務整理を依頼される場合、その分野の経験が豊富な弁護士に依頼することが大切です。
たとえば、破産手続きをとる場合、最終的に借金の支払義務がなくなれば誰に依頼しても同じと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、破産には、同時廃止という簡易な事件と、管財事件という複雑な事件があり、裁判所に納める手数料(予納金)が少なくとも20万円以上異なりますが、どちらに分類されるかが弁護士の力量によって左右される場合が少なくありません。
また、管財事件の中でも予納金額は、自己破産の申立てを行う弁護士の力量によって異なる場合が少なくありませんし、後から管財人にお金を払うよう求められる場合もあります。
また、資料集めや作成のお手伝いの仕方によって、かかる時間が大幅に異なりますので、不慣れな弁護士であれば、何度も資料の作成や収集を行うことになり、長期間裁判所への申立てができないこともあります。
2 債務整理に強い弁護士かを見極めるポイント
そこで、最初の相談で、債務整理に強い弁護士かどうかを見極めるポイントをお話しします。
例えば、破産手続きなどでは、裁判所ごとに運用が異なります。
そこで、各裁判所の運用の違いにどの程度詳しいかは、債務整理に強いか否かを見極める一つのポイントになります。
また、任意整理は、相手の貸金業者等との交渉ですので、貸金業者ごとの運用の差にどの程度通じているかが、任意整理に強いといえるかのバロメーターです。
3 債務整理により新たなスタートをするために
当法人では、日々変化する業者の運用に対応するため、定期的に会議や勉強会を行うなどして、最新の情報を事務所内で共有しています。
借金に追われる日々と縁を切り、新たにスタートするためのサポートをさせていただきますので、借金でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
債務整理について弁護士を選ぶにあたって気を付けるべき点
1 弁護士を選ぶにあたって

債務整理に限らず、弁護士が取り扱う問題は、人生における一大事であることも少なくありません。
だからこそ、弁護士選びは慎重に行うべきだと思います。
もっとも、弁護士選びの基準は必ずしも1つに限られませんので、いくつかの判断要素についてみていきたいと思います。
2 費用
債務整理案件の場合にも弁護士費用は発生します。
借金問題を抱えているわけですから、費用については普通に考えれば安いにこしたことはありません。
ただ、極端に安すぎる費用は、「ちゃんと仕事をしてもらえるのか?」という不安にもつながってくると思います。
そのため、安ければよい、とは言い切れません。
費用に関して言えば、「明確かどうか」ということはある程度判断できます。
費用の説明があいまいで、依頼した後に高額の弁護士費用を取られた、といったことにならないように、費用が明確かどうかは、弁護士選びにあたって気をつけるべき点ということができると思います。
3 経験
たとえば、手術をしてもらうのに、初めてその手術を手掛ける医師に頼むのは抵抗があると思います。
同様に、弁護士に依頼する際にも、債務整理の経験がどの程度あるかは確認すべき点であるといえます。
経験がどの程度あるかということについては、聞いてみないとわかりません。
というのも、弁護士は幅広い分野を扱うことができるからです。
債務整理が得意などと打ちだしている事務所もあります。
また、司法試験に合格する年齢にはかなりの差が出ますので、若いから経験がないかというとそうでもないところがあります。
依頼する前に債務整理の案件の経験がどれくらいあるかを確認してみてもよいかもしれません。
事務所によっては、ホームページに解決実績を掲載しているところもあります。
4 人柄
弁護士業務も、人対人の仕事であることは間違いありません。
価値観は人それぞれだと思いますが、人柄というのは、ある意味では最も重視すべきポイントかもしれません。
穏やかな人がいいという方もいらっしゃると思いますし、厳格な雰囲気に頼りがいを感じる方もいるかもしれません。
これは考え方や相性が出るところですし、弁護士も千差万別です。
人柄を重視して決めるというのも1つの考えかもしれません。
債務整理をするのが遅れることのデメリット
1 債務整理が遅れるケース

個人の方の債務整理について、弁護士への依頼が遅れる場合というのは、二つのケースがあります。
一つは、貸金業者等への返済を延滞したまましばらく放置したケース、もう一つは限界まで返済を継続したケースです。
ここでは、弁護士への債務整理の依頼が遅れるとどういったデメリットが考えられるのかということをご説明します。
2 限界まで返済を継続したケース
限界まで返済を継続したケースとは、つまり生活を切り詰めてどうにか返済資金を捻出して頑張ったということですので、それ自体は責められるようなことではありません。
しかし、経済的更生、すなわち生活の再建という債務整理の目的の観点からは、債務整理が遅れればそれだけ生活の再建が遅れることとなり、それがデメリットとなります。
例えば、勤務先の業績悪化により給料が減額され、その給料では借入金の返済が困難である場合、すぐに弁護士に相談して債務整理の手続に入った場合と、5か月間返済を行った後に弁護士に債務整理を依頼した場合とでは、債務整理という結果は同じですが、後者の場合、5か月分の返済原資を生活再建に充てられないということになりますので、それだけ生活再建が遅れることとなります。
3 返済を延滞したまま放置したケース
返済を延滞したまま放置したケースでは、①遅延損害金が増大する、および②強制執行が行われる可能性がある、という二つのデメリットがあります。
例えば、任意整理の場合、貸金業者等への返済総額は各貸金業者との交渉で決まりますが、遅延損害金の付加も求めてくる業者の場合は、債務整理が遅れるほど遅延損害金は増加していることとなりますので、返済総額も増大することになります。
また、返済を延滞したまま放置していると、貸金業者から支払督促の申立てまたは訴訟提起が行われ、それも放置すると、貸金業者が把握している債務者の勤務先から支払われる給料について差押えが行われる可能性があります。
給料が差し押さえられると、原則として手取りの4分の1が差押債権者への返済に充てられますので、生活が厳しくなるのが通常です。
この場合、差押えを止めるには破産等の申し立てをする必要がありますが、給料を差し押さえられているため、費用の準備も困難なことがあります。
弁護士費用については法テラスを利用できても、予納金は債務者が準備する必要があります。
4 返済にご不安がある方はご相談ください
以上のとおり、債務整理が遅れることにはデメリットがあり、反対に目立ったメリットはありませんので、返済の見通しが立たなくなった場合や、延滞した場合は直ちに弁護士に相談することをお勧めします。
名古屋で債務整理を得意とする弁護士をお探しの方は、当法人までお気軽にご相談ください。
債務整理の手段の適切な選び方
1 債務整理の種類

債務整理の手段は、大まかに「破産」、「民事再生」、「任意整理」の三種類に分けられます。
それぞれにメリット、デメリットがありますので、ご自身の状況や要望にあった手段を選ぶ必要があります。
ただ、自分ではどれを選んだらよいか分からないという方がほとんどだと思います。
だからこそ、債務整理を検討する際は、弁護士と実際に会って、自分の置かれている状況、要望等を伝え、自分に最も合った手段を相談していく必要があるのです。
2 破産のメリット・デメリット
債務整理のうち、破産の最大のメリットは、借金が0になることです。
逆に言うと、過払いや時効等によって借金がなくなる場合を除き、支払いが全くできない場合は、この手段を取らざるを得ません。
破産のデメリットは、全てではないにしろ、一定の財産を手放さなければならないことです。
官報に載ってしまうことや、一時的に一部の資格について制限がかかったり、業務を行えなくなることもデメリットに挙げられます。
また、破産については、借金がなくならない場合もあります。
破産をして借金の返済義務をなくすことを「免責」というのですが、免責には不許可事由があります。
たとえば、借金のほとんどがギャンブルや浪費によるものという場合は、免責してもらえないこともあり得ます。
3 民事再生のメリット・デメリット
民事再生の最大のメリットは、破産と異なり、住宅ローンの残っている自宅を残せるところにあります。
また、破産と異なり、ローンが残っており、所有権留保等の担保権が設定されている場合を除き、財産を残すこともできます。
また、破産で言う免責不許可事由に相当するものもありません。
一方、デメリットは、一定額については、支払いを継続していかなければならないことです。
4 任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリットは、裁判所を介さない手続きなので、対象とする債権者を選べるところにあります。
破産、民事再生は、裁判所が、強制的に借金をなくす、もしくは、減額する手続きなので、債権者間の平等が重視されます。
そのため、全ての債権者を手続きの対象とする必要があります。
これに対して、任意整理は、裁判所を介さず、個別に債権者と話し合い、支払い計画を見直していく手続きになるので、特定の債権者のみ任意整理を行い、他の債権者についてはこれまでとおり支払いを継続していくということも可能です。
このように対象を選べるということは、自動車ローンが残っているけど、自動車は失いたくないという場合や、一部の債務には保証人がついているが、そちらには迷惑をかけたくないという場合に、その債権者のみこれまでとおり払っていくということができるので、そのような方には、大きなメリットになります。
任意整理のデメリットは、債権者の同意が必要なことです。
そのため、過払い等が無い場合には、利息のカットはできても、借金自体の減額ができないことがほとんどです。
支払いの期間についても、4年から5年となることが多いです。
そのため、ある程度の金額を毎月払っていける状態になければ、任意整理を行っていくことは難しいかと思います。
5 債務整理の手段の選択
債務整理の手段として万能なものはなく、どれがよいのかは、その人の置かれている状況や要望等により異なります。
そのため、債務整理に詳しい弁護士に状況等を十分に伝えて相談することが重要です。
当法人は名古屋駅すぐのところに事務所がありますので、名古屋周辺で借金問題にお困りの場合には、ご相談ください。
債務整理が家族や会社等に知られないかご心配な方へ
1 債務整理に関して多くの方が抱えている不安

債務整理をお考えの方が抱えている不安の一つに、家族や会社に借金について知られてしまうのではないかというものがあります。
債務整理手続を行ったことにより、債権者から家族や会社に連絡がなされてしまうのではないかということです。
借金があることそのものや、どこから借金しているか、借金の総額はいくらか等を家族や会社に内緒にしている方は、非常に多くいらっしゃいます。
中には、借金があることが知られると離婚されてしまう、会社をクビになってしまうなどという事情を抱えている方もいらっしゃいますので、借金が知られるかどうかは大変重要な問題です。
2 債務整理を弁護士に依頼した場合
- (1) 債権者からの連絡
-
通常の場合、弁護士に依頼をして債務整理を行った場合でも、債権者から家族や会社に対して連絡がなされることはありません。
債務整理の依頼をする前であれば、支払いが遅れてしまっている場合には、自宅に貸金業者から督促の連絡が来ますし、連絡が取れない状態が続くと、勤務先に連絡が入ることもあります。
むしろ、債務整理を弁護士に依頼することで、債権者からの連絡が弁護士に対してされるようになり、自宅や会社への連絡が回避できるようになります。
ただ、債権者がいわゆる闇金等の場合は、家族や会社に連絡をしてでも回収を図ろうとすることもありますので、慎重な対応が必要です。
- (2) 依頼した弁護士からの連絡
-
依頼した弁護士から連絡等がくることによって、家族に債務整理の事実が知られてしまうのではないかと不安に思われる方もいるかもしれません。
郵便物の差出人を法律事務所名ではなく個人名で送付してもらう、郵送せずにすべて事務所にとりいく、電話は決まった電話番号にしかかけないようにしてもらうなどの適切な対応をとってもらえば、家族に知られるのを避けることが可能です。
3 債務整理の方法によっては注意が必要
債務整理のうち、破産や再生を選択した場合、手続をとっていることが官報に公告されますし、破産手続をとっている場合、本籍地で取得する身分証明書(破産者でないことの証明)に記載をされてしまいます。
置かれている状況に応じて、どのような債務整理の方法が適切かということは異なります。
どうしても借金について周囲に知られると困るという場合は、弁護士に相談する際に、具体的な事情を弁護士に伝えて、弁護士からアドバイスをもらうのがよいかと思います。
当法人では、依頼者の方の秘密を守ることには特に注意を払っています。
名古屋で債務整理をお考えの際は、当法人にご相談ください。
悪徳業者の債務整理には要注意
1 債務整理について無資格の悪徳業者

債務整理を相談する際は、法律の専門家ではない業者が行っている相談にご注意ください。
まず、弁護士や認定司法書士の資格を有していないにもかかわらず、債務整理についてPRしているホームページ、チラシには注意が必要です。
債務整理は法律事務であり、弁護士や認定司法書士以外は取り扱うことはできません。
それにもかかわらず、そのような資格者以外の団体が、債務整理を行うと謳って広告をしていることがあります。
このような悪徳業者の場合、お金を払って契約をしたにもかかわらず、実質的には借金の整理をしていなかったり、より条件の悪いローンにまとめただけにもかかわらず、高額の手数料等を要求されることがあるようです。
2 弁護士・司法書士から名義を借りる悪徳業者
また、悪徳業者の中には、弁護士や認定司法書士から名義だけを借りて業務を行っているようなところもあります。
悪徳業者が弁護士、認定司法書士の名義のみを借りているような場合は、弁護士等と直接会ったり、話したりすることがなく、無資格者が事件を担当することが多いです。
そのため、弁護士や認定司法書士の名前がある場合であっても、弁護士や認定司法書士と直接話すことができるのかどうかは、確認しておいた方がよいポイントだと思います。
特に、弁護士の場合は、日本弁護士連合会の規程で、債務整理の依頼を受ける場合には直接会って面談しなければならないということが定められています。
弁護士事務所であるのに、債務整理の依頼を受ける際に、直接会う必要はないなどというところには注意した方がよいでしょう。
3 利益を追求するあまり効率を重視し過ぎている弁護士や司法書士
弁護士・認定司法書士が業務を行っている場合であっても、利益のみを追求し、その結果、不当に高額な報酬を要求したり、処理しきれない量の債務整理を受け、事件を長期間放置しているようなところもあるようです。
そのため、弁護士・認定司法書士に依頼する場合であっても、報酬は分かりやすいかどうか、後で追加の報酬を請求されないようきちんと契約書を作成しているかどうか、相談したいことができた時や不安になった場合は、弁護士や認定司法書士ときちんと話をすることができるかは確認されることをおすすめします。
このようなことが行われていない場合、後で高額の報酬を要求されたり、弁護士が事件を処理しきれなくなったりしている可能性があります。
4 名古屋で債務整理に関してお悩みの方は弁護士法人心 名古屋法律事務所まで
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅すぐのところに事務所があります。
名古屋の近辺にお住まいの方で、借金についてお悩みになっている方は、お気軽にご相談ください。
弁護士法人心が債務整理を得意とする理由
1 債務整理を得意とする弁護士

名古屋は、全国的にみても多数の弁護士がいる地域です。
彼らそして彼女らは皆、弁護士資格をもった法律のプロです。
しかし、弁護士の取り扱う分野は、債務整理、交通事故、相続、離婚、刑事事件、労働問題など多岐にわたり、いくらプロといっても、全ての分野に高レベルで通じているという弁護士はなかなかいません。
料理人にはそれぞれ得意な料理があるように、弁護士にもまたそれぞれ得意な分野があるのです。
名古屋のような弁護士が多数いる地域において、自信を持って債務整理が得意といえるレベルの弁護士になろうと思えば、日々その分野の事件を担当することで腕を磨き続けなければなりません。
とくに債務整理は手続が複雑であるため、生半可な知識や経験をもとに挑んでしまい、債権者や裁判所への対応を誤ってしまうと、手続の失敗や、財産・給料等の差押えがされてしまうなどにより、依頼者の方が重大な不利益を被ってしまうおそれすらあります。
このような事態にならないよう、債務整理を依頼する際には、債務整理を得意としている弁護士に依頼した方が安心です。
2 弁護士法人心の債務整理に関する取り組み
当法人の弁護士は、取扱分野を絞ることによって、ある特定の分野について集中して腕を磨き、質の高いサービスを提供できるよう、日々事件に取り組んでいます。
さらに、月に複数回、全拠点の債務整理を集中的に取り扱っている弁護士が集まって、研修や情報共有を行っています。
この研修や情報共有では、債務整理の経験が豊富な弁護士がノウハウを共有したり、最近の裁判例の動向のチェックや、裁判所ごとの運用の違いや注意点の確認を行うなどして、日々債務整理に関する知識・情報をアップデートしています。
このような取り組みは、東海地方のみならず、関東地方や関西地方にも複数の拠点があり、多債務整理を集中的に取り扱っている経験豊富な弁護士が多数在籍している弁護士法人心だからこそできることであり、そのような取り組みが依頼者の方に少しでも良質のサービスを提供することにつながっていると考えています。
このように当法人では、債務整理を行う弁護士やスタッフが、名古屋で一番債務整理が得意な弁護士と評価されるよう日々腕を磨き続けています。
このような取り組みの成果として、多くのお客様から選んでいただいており、さらなる知識・経験の獲得につながっています
債務整理に関して困ったことがありましたら、当法人にいつでもご相談ください。
自宅を残したい場合の債務整理
1 債務整理をした場合の自宅の扱い

⑴ 破産手続の場合
破産手続は、破産者が所有している財産をお金に換え、各債権者に対して平等に分配する手続です。
したがって、たとえ自宅のローンを払い終わっていたとしても、破産手続を選択すれば自宅は売られてしまい、残すことはできません。
⑵ 民事再生手続の場合
一方で、民事再生手続の場合には、担保に取られていない財産は手元に残しておくことができます。
住宅ローンが残っている場合も、住宅資金特別条項を使って自宅を手元に残しつつ、住宅ローン以外の借入れについて減額して支払っていくことができる可能性があります。
住宅資金特別条項を使って自宅を残せる場合については、様々なパターンがあります。
2 住宅資金特別条項が使える場合
⑴ 再生債務者が自宅を所有していること
住宅資金特別条項を用いるためには、少なくとも民事再生をする方が自宅の所有権を有している必要があります。
この所有の形態については、単独所有でなく、共有の形でもよいとされています。
⑵ 居住に用いられていること
床面積の2分の1以上が再生債務者の居住に用いられていることが必要です。
第三者に対して賃貸しているなど、自己の居住のために使っていない建物に対しては、原則として住宅資金特別条項を用いることができません。
⑶ 住宅に住宅ローン債権や保証会社の保証債務履行請求権を被担保債権とする抵当権以外の他の担保権が設定されていないこと
住宅ローン以外の担保権が設定されている場合、仮に住宅資金特別条項を使ったとしても、同条項の対象とならない担保権があるため、これが実行されてしまえば結局自宅は残らないことになります。
したがって、このような自宅は、住宅資金特別条項の対象外となっています。
他にも細かい要件はありますが、詳しくはご相談の際、弁護士にお尋ねください。
3 住宅ローンを払い終えている場合の民事再生
住宅ローンを支払い終えている場合も、民事再生手続であれば自宅を残すことができます。
ただ、民事再生における清算価値保障原則に気をつける必要があります。
清算価値保障原則とは、民事再生における返済額は、破産手続によって財産をお金に換えて債権者に分配する金額を下回ってはならないというものです。
住宅ローンを支払い終わっている自宅を売却した際の金額は高額になる場合もありますので、民事再生をした場合の最終的な返済額との関係では注意が必要です。
4 名古屋で債務整理をお考えの方は当法人まで
民事再生手続の件数自体は、破産手続の件数に比べるとかなり少なく、したがって経験のある弁護士の数も限定されてきます。
名古屋でご自宅を残しての債務整理をお考えの方は、豊富な経験を有する当法人の弁護士にお任せください。
支払督促を受けた場合の債務整理
1 支払督促とは

⑴ 裁判所を介した取立ての方法の1つ
債権者である貸金業者が、「支払督促」という制度を使って取立てを試みることがあります。
支払督促とは、裁判所が債権者の申立て内容のみを審査して、債務の支払いを求める手続きです。
支払督促は裁判所から書面が届きます。
債権者が直接送ってきた督促状や法的手続予告通知書などの書面はこれには当たりません。
以下に説明するとおり、支払督促が届いた場合には早急に対応する必要があります。
⑵ 放置するとどうなるのか
支払督促状が届いた場合、送達を受けた日(=受け取った日)から2週間以内に異議の申立てをしなければ、仮執行の宣言が付されてしまいます。
この仮執行の宣言が付された支払督促に対し、適法な異議の申し立てがなされなければ、支払督促には確定判決と同一の効力が認められてしまいます。
つまり、給料や預貯金等の財産を差し押さえられてしまうおそれが出てくるということです。
2 支払督促が届いた場合の対処方法
⑴ 異議の申立てを行う
支払督促が届いたら、2週間以内に異議の申立てを行います。
異議の理由について、例えばもう支払ったとか、時効で消滅しているといった、支払義務が存在しないという理由があればよいのですが、そういった理由がなくとも、債務整理の返済計画の目途をたてるために時間が必要です。
そのため、特に支払義務が存在しない理由がなくとも、とりあえず異議理由については追って主張するというような文言で異議の申立てを行うのが一般的です。
支払督促は、債権者の申立て内容のみを裁判所が審査をするのですが、具体的な証拠等は提出されていませんので、「追って主張する」といった内容での異議申立でも通ることが通常です。
⑵ 異議の申立て後の裁判への移行
異議の申立てが適法になされた場合、債権者が通常の裁判を起こしてくることがあり、その場合には訴状や口頭弁論期日呼出状といった書面が裁判所から届きます。
⑶ 和解又は破産手続・民事再生手続の申立て
支払義務が存在する場合、いずれは敗訴判決が出てしまいます。
そうすると、支払督促を放置した場合と同様、給料等の差押えといった問題が発生します。
給与の差押えがなされてしまうと、給料の4分の1、または、月額の手取りが44万円を超える場合には、33万円を超える部分について差押えがなされてしまい、生活に大きな影響が出てしまいます。
そこで、目指すべき方針としては、判決が出てしまう前に、支払についての和解をすることや破産手続や民事再生手続の申立てを行うこととなります。
3 支払督促が届いたら弁護士にご相談ください
支払督促が届いた場合、適切な対応をせずにのんびりしていては状況がさらに悪くなってしまうおそれがあります。
支払督促が届いたという方は、どのように債務整理をしていくかということを早急に検討すべく、弁護士に相談することが望ましいといえるでしょう。
相談の際は、落ち着いて弁護士に状況をお聞かせください。
名古屋で債務整理をお考えの方は、名古屋駅から徒歩圏内にある当法人の弁護士が丁寧にアドバイスをさせていただきます。
任意整理で主な対象となる業者
1 任意整理とは

⑴ 任意整理のメリット
任意整理は、債権者と弁護士とが交渉を行い、長期の分割払いを認めてもらうようにしていく手続です。
任意整理には、長期の分割や将来利息の支払いを免除してもらえる可能性があるといったメリットがあります。
また、裁判所を通した手続きではないため、多くの資料を収集したり、世帯全体で協力して家計簿を作ったりする必要がありません。
そのため、債務整理をしていることをご家族に知られてしまうリスクは低いといえます。
⑵ 債権者との交渉とは
ア 交渉内容
債権者との交渉では、なるべく長期での分割払いを認めてもらい毎月の返済額を少なくすることや、将来利息や遅延損害金といった、借入れの元本以外の部分を減らしてもらうことを目指していきます。
イ 交渉の相場
この交渉にあたっては、これまでの返済の実績や返済してきた期間がポイントとなることがあります。
また、各貸金業者には、この場合にはこの程度までの分割払いを認めるといったような交渉における相場があります。
任意整理は、業者ごとの特質をよく理解しており、債務整理が得意な弁護士に依頼することが重要です。
各貸金業者も、なるべく短期間で貸した分を回収したいと考えています。
そのため、交渉当初は5年ではなく、より短期間での分割でなければ原則として和解に応じることはできないと言ってくることがあります。
経験がないと、貸金業者のそのような発言を信じてしまい、実際には5年程度の分割払いとなる見込みであったのに、より短期間での分割払いでの和解に応じてしまうことにもなりかねません。
2 任意整理の交渉相手になりうる債権者
⑴ 基本的には業者が相手です
任意整理の交渉が可能な相手は、消費者金融や銀行、クレジットカード会社といった業者です。
⑵ 個人からの借入れについて
個人からの借入れについては、業者との交渉と異なり、交渉における相場がありません。
したがって、弁護士が介入して交渉をすることが必ずしも長期の分割といった効果を上げることにつながるとは限りません。
そのため、個人からの借入れについては任意整理の交渉の相手方からは外すということも視野に入ります。
3 名古屋で任意整理をお考えの方は当法人まで
当法人では、債務整理を取り扱う弁護士でチームを作り、貸金業者の特徴等について情報を集める等、より有利な条件で和解をまとめるためのノウハウを蓄積しています。
名古屋で任意整理をお考えの方は、名古屋駅から徒歩2分の当法人まで、お気軽にご相談ください。
名古屋駅から弁護士法人心 名古屋法律事務所及び弁護士法人心(本部)へのアクセスについて
1 名古屋駅の太閤通り南口から出てください
⑴ JR線・あおなみ線でお越しの方
当法人の事務所に近い改札は太閤通り南口の改札となっておりますので、JR線・あおなみ線でお越しの場合はこちらの改札から出てください。

改札を出た先に出口がありますので、まっすぐ進みそちらから外に出てください。
太閤通り南口以外の改札から出た場合は、⑵をご参照ください。

⑵ JR線・あおなみ線以外でお越しの方
当法人の事務所までは、名古屋駅の太閤通り南口が一番近い出口となっております。
まずは名古屋駅構内にある銀時計を目指してください。
銀時計のある広場に到着したら、「驛弁」と書かれた売店(デリカステーション)がある方向に行き、名古屋驛麺通りの右側にある通路を進んでください。


進んだ先に名古屋うまいもん通り太閤通り口の入口があります。
その入り口の右側に太閤通り南口がありますので、そちらから外に出てください

2 太閤通り南口から交差点までまっすぐ進んでください
太閤通り南口を出た後、横断歩道を渡りカフェ・ド・クリエ駅西口店がある歩道をまっすぐ進んでいただくと、地下道の入り口と駐輪場があります。


そのまま駐輪場のある道を進んでいくと、正面にセブンイレブンがある交差点が見えてきます。

3 横断歩道を渡り、セブンイレブンの前を左折してください
交差点の横断歩道を渡った後、セブンイレブン前を左折してください。
そのまままっすぐ進んでいただくと、スクランブル交差点があります。


4 事務所に到着
⑴ 弁護士法人心 名古屋法律事務所の場合
弁護士法人心 名古屋法律事務所にお越しいただく場合は、正面の横断歩道を渡ってください。
ミニミニがあるビルの4階に当法人の事務所がありますので、中に入りエレベーターでお越しください。

⑵ 弁護士法人心(本部)の場合
弁護士法人心の本部にお越しいただく場合は、交差点を渡らずに右折してください。
まっすぐ進むと、右手にすき家名駅西店がみえてきます。
すき家を過ぎると、ローソン椿町店の手前に「West Point1413」と書かれた緑の入口があります。
そのビルに当法人の事務所がありますので、中に入りエレベーターで7階にお越しください。


駅近くの事務所です
駅から出て徒歩2分ほどでお越しいただくことができる事務所です。写真付きでご案内しておりますので、初めての方はこちらをご覧ください。
栄駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 栄駅中改札口を出てください
栄駅に着いたら、中改札口を出てください。

2 16番出口を目指してください
当法人の事務所は松坂屋の中にあります。
松坂屋に行くには16番出口が近いですので、案内板に従い進んでください。


3 16番出口から出てください
大きく「16」と書かれた黄色い表示が見えたら、階段を上ってください。

4 まっすぐ進んでください
階段を上ると、右手に名古屋三越栄がある通りに出ます。
名古屋三越栄を右手にしたまま、まっすぐお進みください。

5 松坂屋名古屋店本館に到着
横断歩道を3つ渡った先に、松坂屋名古屋店本館があります。
当法人の事務所がある7階までお越しください。

事務所へのご案内
事務所までの道順を、写真付きでご説明しています。こちらをご覧いただくとともに、もしも分からなくなった場合はご連絡ください。
矢場町駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 矢場町駅1・5・6番出口側の北改札口を出てください
矢場町駅に着いたら、案内板に従い1・5・6番出口側の北改札口を出てください。

2 松坂屋方面の通路に入ってください
矢場町駅は松坂屋と直結しています。
北改札口を出ると、右手にMatsuzakayaと書かれた看板がありますので、そちらの通路に入り道なりに進んでください。

3 「本館地下2階」にお進みください
通路を進んでいくと、「本館地下2階」と書かれた入口が見えてきます。
当事務所は本館の7階にありますので、そちらの入口から入り、エスカレーター等でお越しください。

地下から建物までお越しいただけます
駅を出たところに通路がありますので、分かりやすいかと思います。こちらの案内もご参考にしてお越しください。